このたびは「むてんかのこと」に足を運んで頂きありがとうございます。
管理人のKOTOママです。

日本は海に囲まれた国。日本近海を流れる黒潮と親潮等の海流のおかげでプランクトンがよく育ち、豊富な漁場となっているんです。

あー、なんか魚食べたくなってきたなー

私たちは、日本の定められた海域までで採れた魚であれば、日本のものと何の疑いもなく思っていませんか?

え、だってそうでしょ?習ったよね。200海里だったっけ…?
そこでとれた魚は日本のものだよね。

そうですよね。日本の沿岸から200海里内の海は日本が魚をとる権利を持っています。しかし2018年に70年ぶりに改正された「改正漁業法」ではそのあたりの権利が危ぶまれてしまう可能性があるんです

えー、何でー!
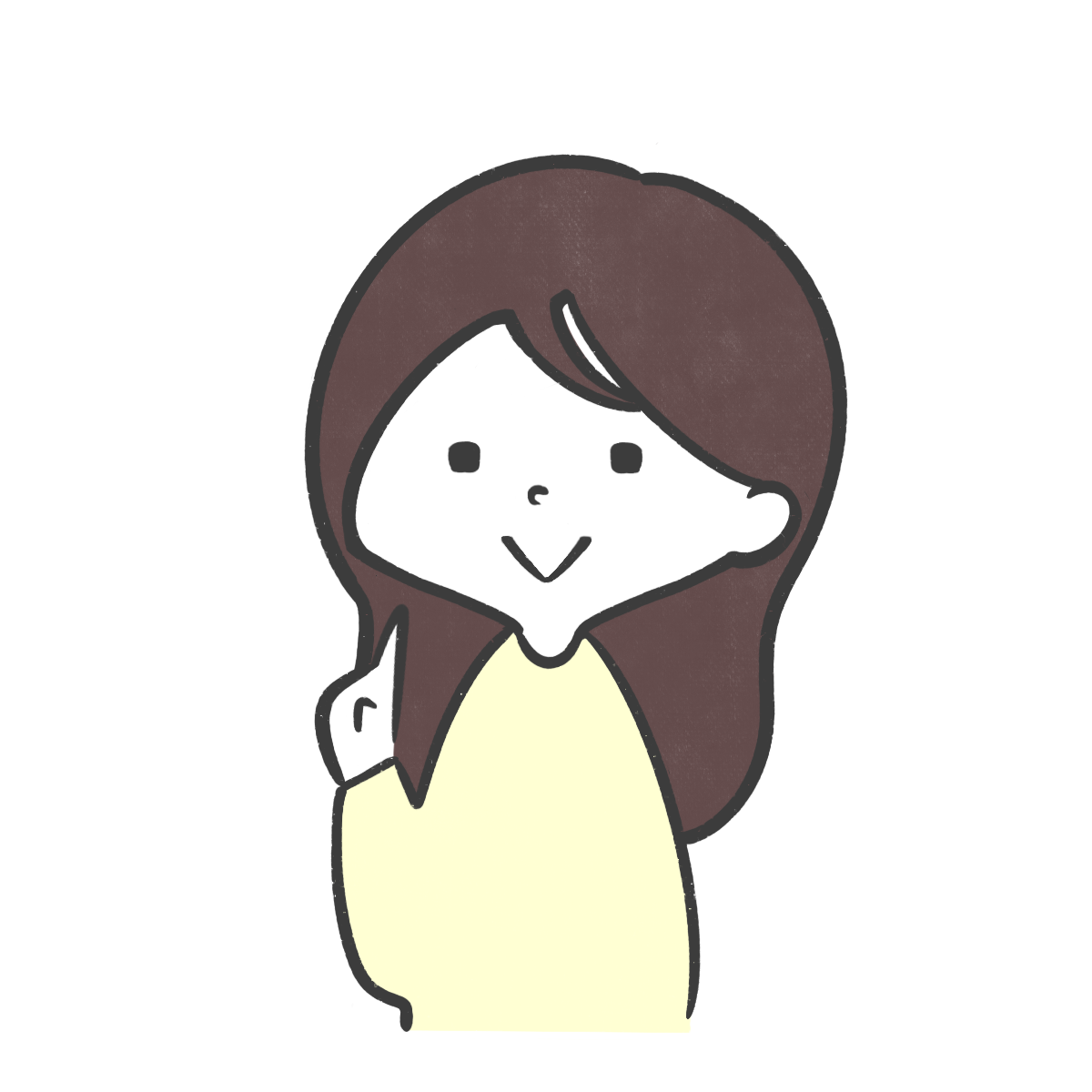
今回は70年ぶりに改正された漁業法について。私たちの暮らしにどんな影響があるのか、書いていきたいと思います。
漁業法改正のポイント

民間企業が参入…悪い予感がするな…

わー…種子法や種苗法と同じような流れになってしまうんだね

そしたら何が起きるのか?その海産物の所有権は…?その企業のものということになりますよね。

そうなるね…

例えば権利を持った企業が中国資本だった場合。中国に優先的に輸出しないでしょうか。

めっちゃしそうだよね
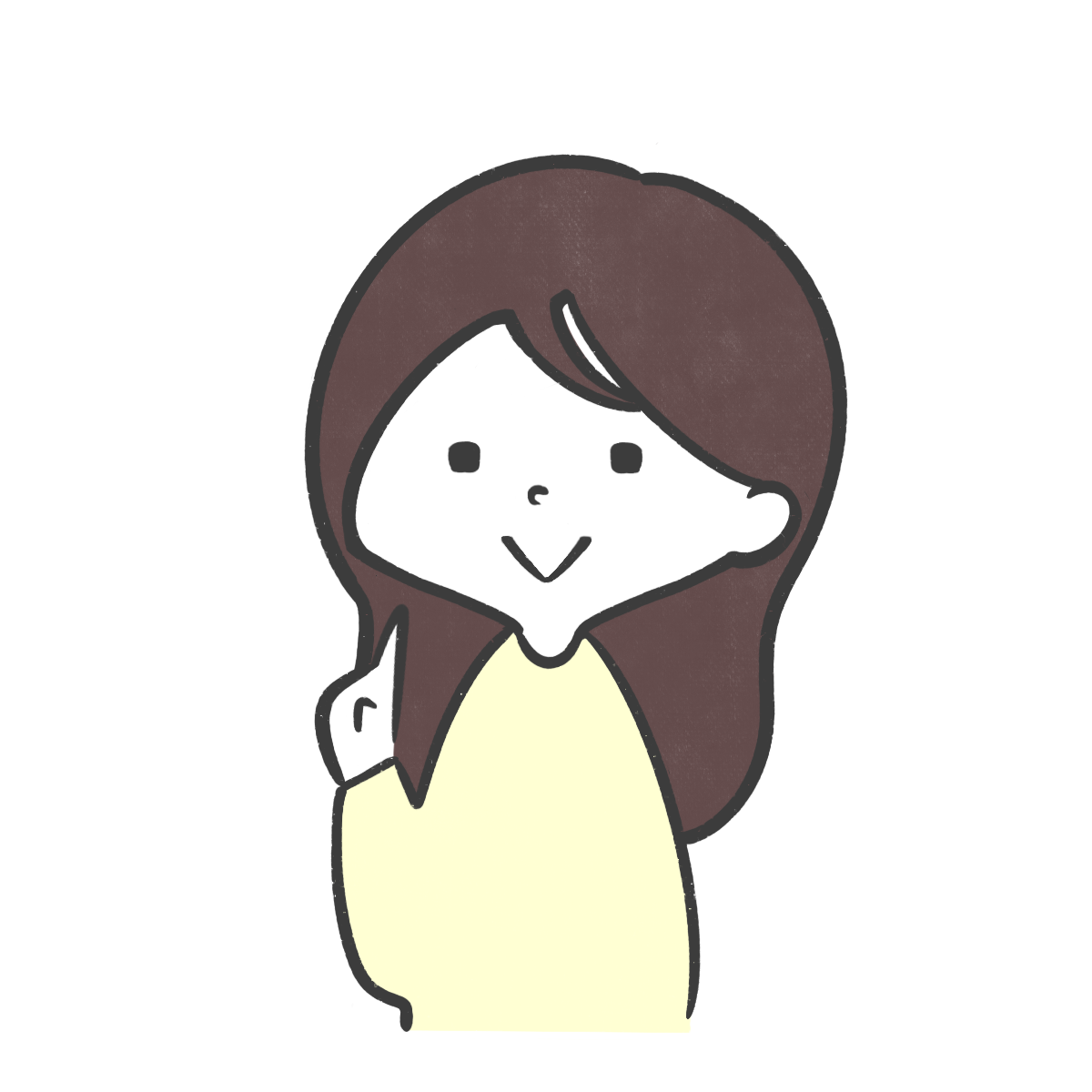
日本で取れた魚が中国に大量に出回ったらどうですか。需給バランスが崩れて値段が吊り上がるってことも考えられる訳です

いや、それは予想出来まくるな
最初に200海里の話をしましたが…

うわー…思っていたよりも深刻な事態だな

これって国防の観点からも大問題だと思う訳ですが…

200海里の中に外国資本が入ってきているって、確かにそうだね。
そもそもなぜこれまで地元の漁協に優先的に割り当ててきたのかというと、地元の漁協の方というのは、地域の現状を把握していますし、漁業者個々人の事情の把握しています。その上で「過密な養殖を防いだり」「他の魚業」に迷惑をかけないよう調整しながら民主的に管理を進めてきたという経緯があるからです。

そこにいきなり、外部の企業が入ってきたらどうでしょうか?その地域全体での資源の管理が出来なくなりますよね。

本当にいいことが全然ない?何でこんなことするの?
30年前に1,000万トンを超えていた日本の漁獲量は500万トン以下。この傾向に歯止めをかけるために「企業に登場してもらい、主に養殖の漁獲量の拡大を狙う」というものです。

建前は…。

出た、たてまえ!!!

この法改正で得をするのは誰かということですよね。
分かっていることは、代々浜を守ってきた漁民の方々と日本国内の消費者ではなさそうということです。
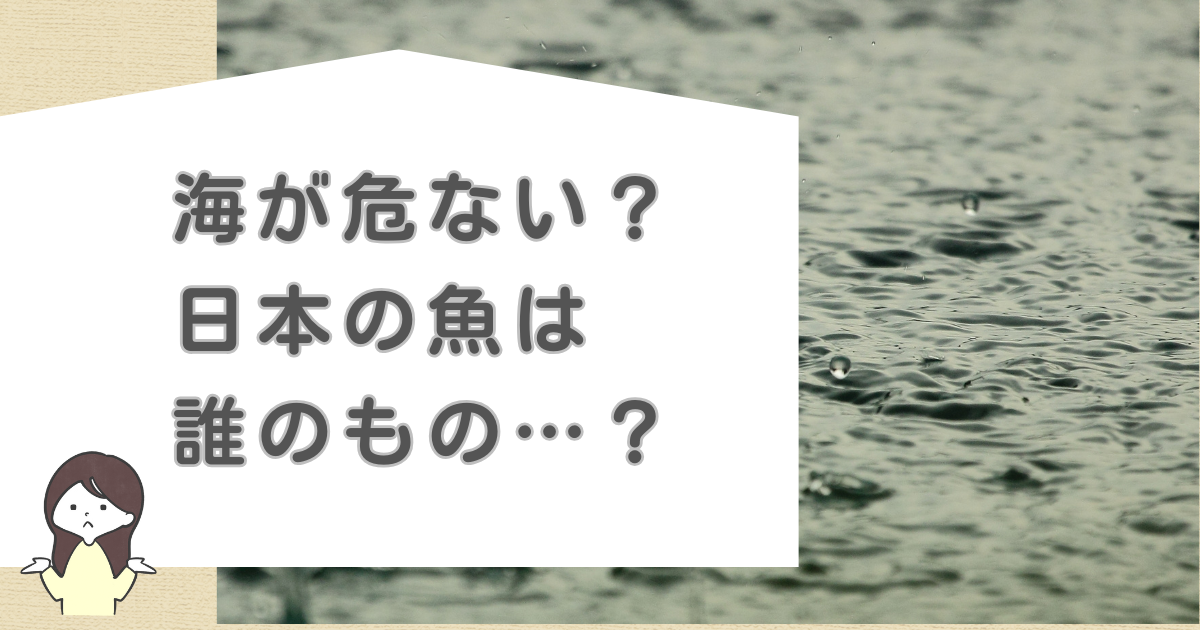



コメント